
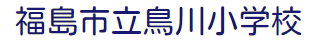



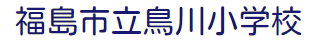

1年生が毎日お世話している、一人一鉢のアサガオ。
7月4日(火)、ついに花が咲き始めました。(一番最初の開花は、先週の木曜日。)
伸ばしたつるから、赤や紫のきれいな花が次々と。
毎日水やりをし、観察してきた1年生は、とてもうれしそうな笑顔を浮かべて、タブレットを使って写真を撮ったり、観察カードに記録したりしていました。
つぼみがついているものもたくさんあるので、まだまだ咲きそうです。
7月の個別懇談のタイミングで、ご家庭に持ち帰っていただきます。
夏休み中、花がいくつ咲くでしょうか。
種がいつくとれるでしょうか。
楽しみですね。











今日7月3日(月)の3・4校時、6年生が総合的な学習の時間で、地域の歴史を訪ねるフィールドワークを行いました。
今回のフィールドワークは、主に学校の東側を中心に、実際に歩きながら、遺跡などを巡ります。
江戸時代に起こった洪水の犠牲になった方々の供養塔
5世紀ころ作られたといわれる「稲荷塚古墳」や「八幡塚古墳」
江戸時代の庄屋「矢吹邸」などなど
毎日、登下校している道や道端にも、歴史的なものがたくさんあることに気づきました。
特に今回は、ラッキーなことに、稲荷塚古墳で発掘調査をしている現場に出くわし、発掘調査員の方から、直接、出土品に関するお話をお伺いすることができました。よかったですね。
次回は、学校の西側を中心にフィールドワークをおこない、その後、学んだことを、ポスターセッションやコンピュータによるプレゼンテーション等で、まとめ・発信していくそうです。
自分の生まれ育った地域の歴史を知ることは、地域への理解・愛情を深めることにつながります。
社会科の授業によって、歴史学習の入り口に立ち、扉を開いた子どもたちが、身のまわりの「ひと・もの・こと」を歴史とのかかわりで考えたり、先人の偉業を学んだりするきっかけになるといいですね。









4年生の算数科は現在、「角の大きさ」の学習をしています。
これまで、180度より小さい角の大きさを分度器を使って測る学習をしてきた2組の子どもたち。
今日7月3日(月)の2校時は、「180度より大きい角は、どのように測るといいのだろうか。」という課題に取り組んでいました。
子どもたちが使っている分度器は半円状のもので、メモリは180度までしかついていません。
さあどうする?
子どもたちは、これまで学習してきた「180度は直線」「180度=2直角」「1回転は4直角」「4直角=360度」であることや補助線を書いて測る経験を手がかりに、どうしたら角が測れるかを考えはじめます。
まずはひとりで、試行錯誤。
すると、どこかから「あ、そうか!」の声。
ペアで話し合いをすると・・・。
「なるほど。」「あぁ~ わかった。」の声がチラホラ。友だちと協力すると、見方・考え方が広がりますね。
自分の考えが持てたら、ワークシートに書き込みます。その後、写真にとり「メタモジ」を使って学級全体で共有です。
その結果、「補助線を引いて180度を作り、180度に残りの角度を足すやり方」と「360度から引いて求めるやり方」の2通りの求め方を子どもたちは導き出すことができました。
「初めて出会う問題場面でも、今まで学んできた知識や技能を使えば、解決することができる。」
日々の授業の中、このような学習経験を繰り返すことで、子どもたちは、自ら考え、自ら問題を解決していく資質や能力を鍛えています。








【鳥川小教職員勤務時間】
8:10~16:40
~留守番電話の運用について~
以下の通り留守番電話の設定をいたします。
(1)週休日・休日⇒終日
(2)学校閉庁日⇒終日
(3)17:00から
平日の朝は、7:30頃に留守番電話を解除いたします
こちらからアクセスしてください。