
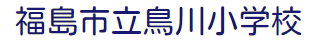



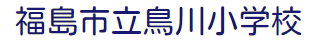

1年生の算数科は現在、「なんばんめ」について学習をすすめています。
「前から〇ばんめ」「前から〇つ」などの言い方で、並んだものの場所や位置を言い表す学習です。
今日6月19日(水)の5校時、1組の子どもたちが、「前後」「左右」「上下」などの方向や位置をあらわす言葉に着目し、これらの言葉を正しく使って、ものの順序や位置を言い表す学習に取り組みました。
前の時間までは、列に並んでいる人や動物の絵を見て、「前から」や「後ろから」という言い表し方を学習をしてきた子どもたち。
この時間は、教科書に掲載されている、6階建てのビルにいる動物たちや横一列に置かれている果物、教室の座席の順序や位置の言い表し方を考えます。
さあ、どんな言葉を使うと、言い表せるかな?
自分の考えをワークシートに書いてみよう。
「パンダは、上から2番目だよ。」
「ぼくは、下から5番目って書いたよ。」
書けたら、友だちと比べてみましょう。 同じかな? 違うかな?
「右から? 前から?」
「前からでいいの? 上からじゃないの?」
そう書いたわけをお話ししよう。
お友だちの理由も聞いてみよう。
「えっ、これって何て言えばいいのかな???」
「わたしは、上から2番目で、右から3番目って書いたよ。」
「えっ、そう書いてもいいの?」
お友だちの考えを聞くことで、新たな気づきがありますね。
また、比べて違いがあると、もやもやして、確かめたくもなるよね。
書くスピードが上がっていたり、ペアのお友だちと声の大きさを考えて話したり。
発表の際は、お友だちの方を見て、真剣に話を聞く姿にも、これまでの学習の積み重ねを感じました。
入学して2か月。ずいぶとみんな、お兄さん・お姉さんになりましたねぇ~。
進んで課題に取り組む1組の子ども達の姿が、たくさん見られた授業でした。
「右から」「左から」「何ばんめ」「〇からいくつ」などの言い方は、ふだんの生活の中で意識的に使うことで、身についていくものです。
「右から4冊、本をとってね。」
「下から2つ目の引き出しを開けて。」
「上から3つ目のボタンは何色?」等々。
ご家庭でも、方向や場所、位置、順序を意識した会話を心がけていただけるとありがたいです。いい復習になります。
昨日に引き続き、今日のこの時間も校内研究授業。
指導助言の外部講師(福島市教育委員会指導主事 遠藤義武 先生)にも参観していただき、放課後は、参観した先生方でよりよい授業の在り方について研修しました。
先生方も、学んでいます。








3年生の国語科は現在、「わにのおじいさんのたから物」の学習をしています。
今日6月18日(火)の5校時、2組の子どもたちが、わにのおじいさんは、どうしておにの子に宝物の場所を教えたのかを考え、話し合いました。
まずは一人読み。
わにのおじいさんが、おにの子に宝物の場所を教えた理由について、わかる部分を本文から見つけてサイドラインを引き、そう考えた理由を教科書にメモします。
理由を書いた後は、近くのお友だちと交流です。
「おにの子なら、大切にしてくれると思ったんじゃないかな。」
「心おきなくあの世に行けるって書いてあるから、安心したんじゃない。」
「おには、葉っぱをかけてくれてやさしい。お礼の気持ち。」
「ていねいにしゃべってくれているし、やさしい人だと思う。」
「わには、これで、もうねらわれなくてすむって思ったんじゃないかな。」
様々な視点での意見が出されていました。
同じ言葉に着目したとしても、話し合いをしてみると、感じ方・考え方の違いがあることがわかりました。
また、お友だちの意見を聞くときには、うなづいたり、反応を返したりするなど、発言者の内容を聞き取ろうとする姿勢が感じられ、とても感心しました。昨年度からの積み上げの成果ですね。
授業の終わりには、「あぁ、楽しかった」という子どものつぶやきが聞こえてくる授業でした。
次の時間は、紹介カードを書いて、物語の感想を伝え合います。
「面白い」って感じる部分、人それぞれ違うかもね。
今回の授業は、校内研修の場でもありましたので、指導助言の外部講師(福島第三小学校 矢内先生)にも参観していただきました。
放課後は、参観した先生方で授業研究を行い、多くの学びがある一日になりました。














今日6月18日(火)の3・4校時、4年2組の子どもたちが、図画工作科の学習で、「ギコギコ・トントン・クリエイター」に取り組んでいました。
のこぎりで切ったり、釘を打ったりして、角材の形を変えながら自分が作りたいものを作る活動です。
図工室のあちこちで、ギコギコという音。木はけっこう堅いようです。
最初は、なかなか切れないよ~と悪戦苦闘していた子も、要領をつかむと、どんどんのこぎりを引いていました。
やがて四角や三角の「つみき」がたくさん出来上がると、紙やすりを使って、表面を滑らかに…。
みんな、ケガもなく無事にギコギコできて、良かったですね!
次の時間は、金づちをつかって、くぎ打ちです。どんな作品が出来上がるのでしょう。楽しみです。






6年生は、6月27日(木)から1泊2日の予定で、修学旅行に出かけます。
その2日目には、班ごとに会津若松市内を散策し、昼は、自分たちでレストランや食堂などに入って、食事をとるという計画です。
そこで今日6月17日(月)の午前中、子どもたちがグループごとに話し合い、代表者が、当日お世話になるレストラン等に、職員室から電話で予約をいれる活動に取り組みました。
緊張しながらも、大事なことがもれなく伝わるようメモをもとに電話します。
自分は、どこの学校の、何と言う名前なのか。
いつごろ、何人で訪問するのか。
そもそも、予約は可能なのか・・・
さすがは鳥川小の6年生。ドキドキしながらも、礼儀正しい言葉遣いで、きちんと会話することができています。
無事に予約が取れると、ホッとした笑顔が・・・。緊張するけど、良い経験ですね。
電話での印象もとても大事です。
修学旅行は、もう始まっています。








算数科の学習で、巻尺の使い方や巻尺を使うとよい場面について学んだ3年1組の子どもたち。
今日6月17日(月)の2校時、実際に教室にあるもので、測りたいものの長さを測る活動に取り組んでいました。
巻尺が斜めになってしまったり、たるんでしまったりしないように、ピンと張ってメモリを読みます。
一人で測ることができないところは、友だちと協力しながら、長さを測りました。
ロッカーの横の長さを測ってみたり、掃除用具入れの高さを測ってみたり・・・
ものさしとは違い、曲面上の長さを測定できることにも気付きました。
実際に測るときには、「8m50cmくらいかな。」「10mよりも短そうだぞ。」と予想を立ててから測ることがポイントです。そうすることで、長さの感覚を養っていくことができます。
「掃除用具入れの高さは、2mぐらいだと思っていたけど、1m80cmだったよ。」
「黒板の横の幅は、予想とだいたい同じで、3m60cmだった。」
実際に測る活動を積み重ね、楽しみながら学習に取り組んでいました。








こちらからアクセスしてください。