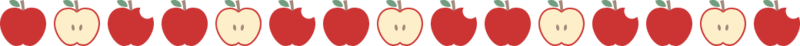
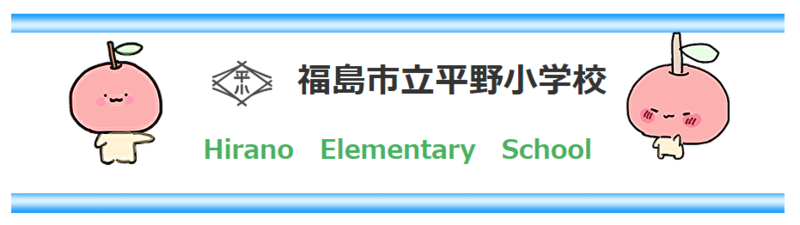
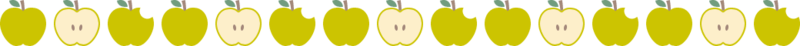

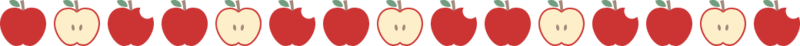
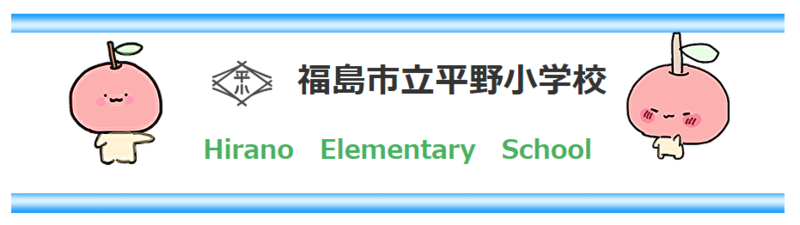
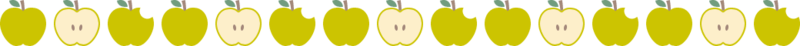
6年生は、1月31日水曜日に、体育館で縄跳び記録会を実施しました。
まず、各自が2種目を選び、それぞれ2分間の間にできるだけ多く続けて跳ぶことに挑戦しました。
二重交差跳びや、後ろはやぶさ跳びなどの難しいとび方にチャレンジしている児童もいました。
次に6分間持久跳びに挑戦しました。
今までに6分間を跳んでいる児童は、赤帽子、まだ跳んでいない児童は白帽子で跳び始めました。
今日はじめて6分間跳びに合格できた児童もいました。
最後に各学級の赤、白に分かれて長縄跳びをしました。
6チームすべてが3分間で200回以上跳ぶことができました。
小学校最後の縄跳び記録会、全力で取り組むことができました。
保護者の方の応援、ありがとうございました。
来年1年生になる子どもたちと仲良く交流しました。
ランドセルを背負ったり、アイパッドを操作したり、お店屋さんやじゃんけん列車など、子どもたちのアイディアで楽しく交流することができました。
今日の昼休み、5年生の図書委員による読み聞かせの会が開かれ、たくさんの子供たちが物語の世界を楽しみました。
図書室の席が足りなくなるほどの大盛況でした。
1/30(火)、4年生のなわとび記録会が行われました。
持久とびは昨年から1分間増え、4分間となりました。本番ではじめて4分達成できた児童もいました!
種目とびではそれぞれが選んだ種目を何回続けてとぶことができるか挑戦しました。
長なわ8の字とびでは1組・2組・3組すべての学級で最高記録を更新しました!
司会・進行、めあて発表、感想発表も頑張りました。
2月25日から29日まで、アオウゼにて、特別支援の子どもたちの作品が展示されました。
平野小のひとみ•かがやき学級の子どもたちの作品も飾られ、たくさんの方に見ていただきました。
学習の成果や好きなことをお披露目できる良い機会となりました。
3年生は、1月29日 4時間目に、なわとび記録会を行いました。
朝から、どこかそわそわしていた3年生。3時間目の授業を終えると、すぐに準備を開始!
開会式では、各クラスの代表の子どもたちがめあてを発表しました。
準備運動をして体をあたためたら、いよいよスタートです。はじめは、3分間持久跳びを行いました。「あともう少しだった…」と悔しい思いをしてしまう子もいれば、「3分間とびきった!」とよろこぶ子の姿もみられました。しかし、どの子も自分のめあてに向かって一生懸命頑張りました。種目跳びでも、最後まであきらめずにとび続け、自己ベストを達成する子がたくさんいました。
最後はクラスのみんなと息を合わせて、長縄に挑戦しました。「ハイ!ハイ!」とかけ声をかけたり、成功したときはみんなで拍手をして喜んだりしていました。
閉会式では、「3分間とぶことができてうれしかった。」などの感想がありました。
子どもたちにとって、目標に向かって頑張ることができたなわとび記録会になったと思います。
そして、保護者の皆様、お忙しいなか子どもたちへの応援ありがとうございました。
昨年の11月末に福島市社会福祉協議会様より本校へ児童の教育活動に資するため、交付金をいただく機会を得ました。こちらは、平成6年2月から毎月、飯坂の地域福祉のためとご寄付をくださっていた「町内一主婦」の方からのご厚意によるものです。これまでに平野小学校の児童が等しく活用できるようにと検討を重ねてまいりましたが、この度1年生から6年生まで、特別支援学級も含め全学級にCDラジオを購入し配当する運びとなりました。後日、体育館などでも活用できるプロジェクターも納品される見込みです。改めまして、一主婦様のご厚意に感謝し、大切に使ってまいりたいと思います。本当にありがとうございました。
図書委員会のイベント、本の福ぶくろの貸し出しが行われました。
「生き物の好きな人へ」「冒険が好きな人へ」「あっとおどろきたい人へ」などの題名がついた福ぶくろが50個。
図書委員が選んだ本が3冊ずつ入っていますが、中は見えません。
1年生から6年生までが図書室にたくさんやってきて、どれにしようかと楽しく選ぶ姿が見られました。
図書委員の思いが伝わり、本を楽しむ友達がますます増えています。
今月31日に、ひらの認定子ども園と平野保育所の年長さんをお招きして、交流会を行います。
「学校のことを教えてあげよう。」
「仲良くなりたいな。」
「ネームカードを作ろうかな。」
「お手紙も書こう!」
子どもたちのアイディアをもとに計画し、着々と準備を進めています。
すてきな交流会になりますように。
4年生,総合的な学習の時間に「認知症サポーター養成講座」を実施しました。安心・安全ネットワーク平野の方と飯坂南地域包括支援センターの職員の方に認知症について教えていただきました。
グループワークで認知症の人との接し方を話し合い,実際に代表児童が高齢者役の担任などを相手に実践しました。
【平野小教職員勤務時間】
8:10~16:40
留守番電話の運用について
以下の通り留守番電話の設定をいたします。
(1)週休日・休日⇒終日
(2)学校閉庁日⇒終日
(3)毎週水曜日⇒17:30から
(4)その他の平日⇒18:30から
平日の朝は、7:20頃に留守番電話を解除いたします。
【平野小相談室より】スクールカウンセラー
相談室は、お子さんに関わる様々なことを気軽に相談できる場所です。ご遠慮なくご利用ください。相談の内容は相談された方の了解なく、他言いたしませんのでご安心ください。相談を希望される方は、担任か教頭までご連絡ください。
毎週水曜日 10:30~15:00
〒960-0231 福島県福島市飯坂町平野字石堂10番地
TEL 024-542-2732
FAX 024-543-1164